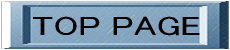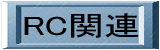1.はじめに
以前試作した防犯ブザー改造の機体発見ブザーは、安く作れて音も大きく好評でしたので、第2段を製作することにしました。
今回使用した防犯ブザーは、前回試作のものより薄型になっています。
2.機能
●機体発見ブザー
(送信機からの信号が途絶えた時でも間欠でブザーが鳴ります)
3.仕様
●動作電圧 3.6〜6.0V
●消費電流 1mA(ブザーオフ時)/35mA(ブザーオン時)
●外形 40*65*20(縦*横*高さ)
●重量 25.7g(コネクタ含む)
●音圧 110dB
4.回路図
5.部品表
| 部品番号 | 品番 | メーカー | 備考 |
| IC1 | PIC12C509A-04/P | マイクロチップ・テクノロジー | . |
| Q1 | RN1202 | 東芝 | . |
| Q2 | RN1225 | 東芝 | . |
| D1 | 1N4002 | VISHAY | 0.5A以上のシリコンダイオードなら何でも良い |
| C1 | 積層セラミックコンデンサ 0.1uF 25V | . | . |
| R1 | 抵抗 470Ω | . | 追加 |
| その他 | 防犯アラーム | ダイソー | . |
| その他 | コネクタ、ユニバーサル基板 | . | . |
6.組み立て
6.1
まず、100円ショップ・ダイソーで防犯アラームを買う。
価格は、200円(税込み210円)だった。以前買ったものは100円だったが、音も大きくなって衝撃にも強くなったと書いてあるし、少しスリムになったので、まあ良しとする。写真のものは白色だが、ケースの色は、黄、シルバーなど数種類あった。
6.2
裏蓋のネジを外して、電池とひもを取り外す。
6.3
電池の端子とソケットスイッチを半田ゴテを使って外す。ソケットスイッチは、端子が基板に食い込んでいてなかなか外せなかった。
ソケットスイッチは、スイッチの樹脂部分を分解(破壊)してから、半田で端子のみを外した方が楽かも知れない。
6.4
次に制御回路を組み立てます。
ユニバーサル基板を下の写真のような形に切ります。
今度のユニットは制御回路を収めるスペースが小さいので、基板もぎりぎりまで小さく作る必要がある。
6.5
トランジスタQ1、Q2のリードを写真のような形にフォーミングする。このようにすると基板の奥まで差し込むことができます。
実装する部品はなるべく深く差し込んで、基板全体の背の高さを低くする必要がある。
6.6
配線図
マイコンは、プログラム書き込みを行なってから、実装します。
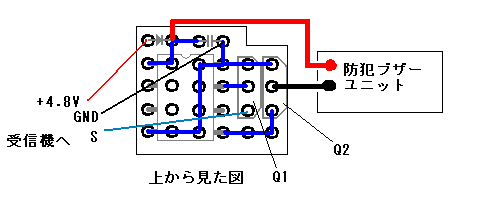
6.7
制御回路完成
写真ではICソケットを使っていますが、ICソケットは不要。
6.8
電線接続
6.9
防犯ブザーとの接続
写真において、防犯ブザーと接続している。電線の色(赤、黒)は回路図、配線図上の色と同じ
6.10
制御回路をバッテリースペースに押し込む。
振動で誤動作しないように基板とケースを合成ゴム系接着剤等で固定しておくと良い。
6.11
裏蓋をネジしめして完成!!
7.マイコン プログラムのダウンロード
自作する方は、マイコンにプログラムを書き込む必要があります。
圧縮形式ですので、下記ファイルをダウンロードした後、解凍してHEXファイルにしてからマイコンへの書き込みを行って下さい。
bz2000.zip
※コンフィグレーション ビットをマニュアルで設定する場合には下記のように設定して下さい。
oscillator : internal rc
watchdog timer : on
code protect : off
master clear : internal
8.使い方
受信機に接続するだけで機体発見ブザーとして動作します。
パルス信号幅が1.3msec以下になるとブザーが鳴るように設定してあり、送信機のスティックがニュートラル付近ではブザーがオン/オフしないようにしてあります。
送信機からの信号が無くなった場合でも、間欠のブザー音が鳴ります。
追記
PCM方式のプロポの場合は、フェールセーフモードにして、送信機からの信号がなくなったときでもブザーが鳴るポジションに設定して下さい。
9.キットについて
機体発見ブザーを作ってみたいけど部品集めが大変、マイコンの書き込みツールを持っていない、という方のために、BZ20の回路部のみのキットを用意しました。キットは、shop2で購入できます。
9.1キットの中身
左からプリント
9.2部品のフォーミング
RN1202とRN1225のリードを写真のように45度に開く。何度も曲げるとリードが折れるので注意して下さい。
ラジオペンチを使って写真のようにリードを加工する。リードの根元が折れやすいので注意。
ダイオード(1N4002)を写真のように曲げる。(ダイオード本体には、必ずカソードマークがありますので、カソード側を曲げます。)
9.3 部品実装
図のように部品を基板上に実装し、裏面からハンダ付けします。
PIC12C509Aの取り付け方向を間違えないように。
9.4 電線の取り付け
電線を取り付ける前に電線の被覆を剥いて導線部分をハンダメッキしておきます。
写真のように基板に電線をつけます。左が赤、右が黒です。
電線は1.5cmくらいの長さで切断し、被覆を剥いておきます。
勿論、導線部分はハンダメッキしておきます。
9.5 コネクタの取り付け
コネクタの電線は、写真のように中央の赤線を5mmほど他の線より長くします。
電線の被覆を剥いて導線は2mmほど出します。
導線は、ハンダメッキしておきます。
電線の色は、左からオレンジ、赤、茶です。(JRコネクタ)
フタバコネクタでは、左から白、赤、黒となります。
基板のハンダ面にコネクタ電線をハンダ付けします。
あらかじめ基板のパッドには、ハンダを盛っておきます。
写真のようにオレンジと茶色の線を先につけるとやり易いです。
最後の赤色の線をつけます。
9.5 防犯ブザーユニットとの接続
写真のように接続します。
防犯ブザーのソケットコネクタは、あらかじめ外しておく。(本文参照)
9.6 ケーシング
回路を収めるときに邪魔になるので、写真の矢印部分をラジオペンチ等を使って取り除いておくと良いです。
写真のように回路を収める。
合成ゴム系接着剤等で固定すると振動対して強くなります。
ケースのフタをするとき、しっくりしまらない場合は、写真の矢印部分を取り除くと良いです。
10.追記
マイコンのGP2とQ2の間に抵抗R1を追加しました。その理由は、Q2のベース電流が大きすぎると何故かGP0の内部プルアップ電圧の低下が見られたためです。最悪の場合、パルス入力がマイコンのしきい値電圧以下になり、入力を受け付けなくなる場合があることが判明しました。キット品では、基板上にチップ抵抗を実装済みです。